第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
道路交通法施行規則 第九条の二の二
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
上記は普通自転車の基準です。ロードバイク、ママチャリをはじめ大半の自転車は普通自転車に含まれますが、普通自転車ではない自転車も身近に存在しています。マウンテンバイク、ファットバイク、ビーチクルーザー等はハンドル幅が60cmを超えるものも多く、リカンベントには幅、長さ共に普通自転車の基準を超えているものがあります。私が所有している自転車の中にも普通自転車の基準を超えるものがあります。そこで、普通自転車と普通自転車ではない自転車の交通ルールの違いをまとめました。普通自転車と普通自転車ではない自転車によってルール違反を咎められるようなことはないと思いますが、ルールではどのようになっているのかを知っておくことは有意義だと思います。
この記事は私個人が法令を調べてまとめたものです。この記事の内容に沿って走行したことにより法令違反を問われても責任を負えません。ご自身でも法令を確認し安全運転に努めてください。
※当記事は令和五年七月一日改正の道路交通法に沿って内容を更新しました。現行の法令とは若干の違いがありますので令和五年七月一日以前に当記事を参照される際にはその点ご留意ください。
※当記事は令和五年七月一日改正の道路交通法に沿って内容を更新しました。現行の法令とは若干の違いがありますので令和五年七月一日以前に当記事を参照される際にはその点ご留意ください。
歩道通行について
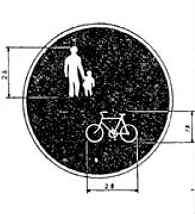
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
道路交通法 第六十三条の四
普通自転車ではない自転車は歩道を通行することができません。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
道路交通法 第二条第三項
第一条の八 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
一 長さ 百九十センチメートル
二 幅 六十センチメートル
道路交通法施行規則 第一条の八
二輪、三輪で側車付きでなく、他の車両を牽引していなければ押して歩くことで歩行者となるため歩道を通行することができます。
また、四輪以上であっても普通自転車サイズであれば押して歩くことで歩行者となるため歩道を通行することができます。
普通自転車専用通行帯について

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
道路交通法 第二十条
普通自転車専用通行帯
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一 (第二条関係)
(327の4の2)
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
普通自転車専用通行帯は普通自転車ではない自転車を対象にしたものではありませんが、普通自転車専用通行帯が道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯である場合には、道交法二十条により普通自転車ではない自転車も普通自転車専用通行帯を通行する義務があります。
自転車道について
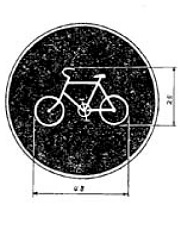
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
道路交通法 第二条第一項第三の三
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
道交法 第十七条第三項
第一条の八 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
一 長さ 百九十センチメートル
二 幅 六十センチメートル
道路交通法施行規則 第一条の八
第五条の六 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
道路交通法施行規則 第五条の六
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
道路交通法 第六十三条の三
普通自転車ではない自転車は以下のいずれかの条件を満たす場合に自転車道の通行を許されています。自転車道を通行する義務はありません。現実的には物理的に可能であれば自転車道を通行し、不可能であれば自転車道ではない車道を通行することになると思われます。
・二輪または三輪
・四輪以上で普通自転車サイズ
自転車専用道路、自転車歩行者専用道路について
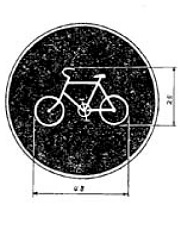
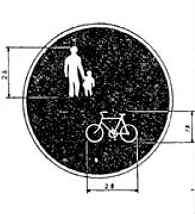
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
道路法 第四十八条の十五
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
所謂サイクリングロードについてです。普通自転車ではない自転車の通行は禁止されていません。
自転車通行止めについて
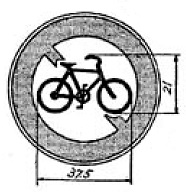
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
道路交通法 第八条
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一 (第二条関係)
(309)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。
普通自転車ではない自転車も自転車通行止めの規制対象です。
特定小型原動機付自転車・自転車専用、普通自転車等及び歩行者等専用(交通法第八条第一項)
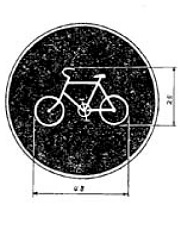
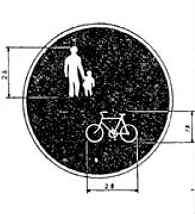
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
道路交通法 第八条
特定小型原動機付自転車・自転車専用
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一 (第二条関係)
(325の2)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。
普通自転車等及び歩行者等専用
(325の3)
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。
普通自転車ではない自転車は通行禁止です。
自転車専用道路、自転車歩行者専用道路と同じ標識が用いられますが、普通自転車ではない自転車の通行の可否に違いがあります。どちらの標識であるか判別できない場合には通行を見合わせた方がよいでしょう。事前に下調べしておくことをおすすめします。
令和五年七月一日の改正により「特定小型原動機付自転車・自転車専用」については以下条件を満たしている普通自転車ではない自転車も通行できるようになります。
・二輪または三輪
・四輪以上で普通自転車サイズ
「普通自転車等及び歩行者等専用」については全ての自転車が通行できるようになります。
自転車専用道路、自転車歩行者専用道路と同じ標識が用いられますが、四輪以上で普通自転車サイズを越える自転車の通行の可否に違いがあります。どちらの標識であるか判別できない場合には通行を見合わせた方がよいでしょう。事前に下調べしておくことをおすすめします。
コメントさせていただきます。
自転車のルールを理解する上で、「普通自転車」か、そうでない自転車か。は重要な視点ですが、一般の自転車利用者はもちろん、警察でさえ「普通自転車」という言葉すら知らないことが多いです。
自分が乗っている自転車が、万が一普通自転車に該当するなら、歩道通行が例外的にできるかもしれないのに・・・。(皮肉です)
私も、仕事がら、普通自転車について勉強していますが、こちらの日記で、とても有意義な情報を書いてくれていますので、参考になります。
ちなみに、2020年12月に、普通自転車の定義が変わり、それまで、2輪、3輪だったものが、4輪以下の自転車になったようです。
ほとんどの自転車利用者には影響のない変更ですが、念のためお知らせしておきます。
リンク先の「道路交通法施行規則 第九条の二の二」で法令を見ても現在の法規がわかるので、読者が勘違いすることは無いと思いますが。
また、最近、勉強したのは、普通自転車の細かな仕様について、ブレーキレバーは、正常者乗車姿勢で、肩より下にないとならないようです。私も、アンダーハンドルではないリカンベントを所有しているので、サイズ以外に気になるところです。
こちらは、普通自転車の型式認定を取る場合の規準です。
「普通自転車の型式認定規準」(道路交通法の改正と共に、こちらも変更があった)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/20201201katashikihutsuu.pdf
この型式認定規準が法的な普通自転車の規準になるのかどうか、はっきりしない部分もありますが、少なくとも、この基準を満たしていれば、普通自転車になると思います。
以上、参考まで。
補足説明感謝いたします。
ですが施行規則第三十九条の五にて
と強制ではなく任意であること、また、型式認定を行っている日本交通管理技術協会にて
https://tmt.or.jp/examination/index.html
と、利用者の便宜が趣旨であるとされていることから、これら基準は普通自転車の必須要件ではないと考えています。
(サドル座面長さ35cm以下ってリカンベントは全滅ですね…)
質問です
『第五条の三 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の五に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
道路交通法施行規則 第五条の三』
とありますが、リンク先にそのような記述がありません
「四輪以上」という記述も他サイトでも見かけたのですが普通自転車の基準に四輪以上という規定は存在する(した)のでしょうか
知る範囲ではかつては2ないし3輪で改定され4輪以下になったと思っています
(一輪車も普通自転車になった?!のでしょうか、ここ気になって調べています)
法改正で条が変わってリンク先がずれているようです。道路交通法施行規則 第五条の六をご覧ください。条文の意味するところは変わっていません。(記事は修正しておきます)
認識されている通りです。こちらWikipediaの記述がわかりやすいかと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%BC%AA%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A
自転車は「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車…」と定義されているため、一輪車は普通自転車には含まれません。